スニこの記事では、
- 棒ノ折山への中継地点であるゴンジリ峠・山頂間、その他の急な登り・階段を通る際、ワークマンスニーカー(アウトドア仕様のもの)で行こうと考えている方
- ゴンジリ峠にある案内板「関東ふれあいの道」ってどこからどこまでなのかな?っと思ったことがある方
のお役に立つ情報をまとめています。
私自身がそういう方…に当てはまるのですが^^;
軽〜くラフな感じで色んな山を歩いてみたい!と思うので、いつもできるだけ「気軽に、楽しく、ワクワク」しながら、生きていきたいと常々思っているのですが、山歩きの時はできるだけ効率よく体を動かし、疲れにくい方法で山に登って帰ってきたいと思っています。
私はリハビリが専門なので、効率のいい体の動作を考えて動かしたり、指導したりするのが仕事の一つです。だからなのかは分かりませんが、遊びでも趣味でも動作の観察をするところから始めるのがクセなんですよね。
自分で山歩きをするようになってから、山を歩いては考え、トライ&エラーを繰り返してきたような気がします。
だから、私の経験と知識をあなたのお役に立てる情報にまとめてみようと思ったわけです。
「山歩きを始めたばかり。これから始めようと考えている!」
そんなあなたのお役に立てたらこんなに嬉しいことはありません(๑>◡<๑)
【棒ノ折山ゴンジリ峠〜山頂】ワークマンスニーカーでの歩き方のポイント3つ
ワークマンのスニーカーの中でも、できれば防水機能がうたわれて販売されているものがいくつかあります。棒ノ折山のような沢を渡ったりする場所があるところでは、スリップが心配されます。その為、これから話す【ポイント3つ】の前に、スリップについて考えておいた方がいいですよね!
まず、あなたが履いている、または履く予定のスニーカーを雨の日に履いたことがありますか?
その確認をしましょう!私も試着した際に、スニーカーによってグリップ感が違うということがありました。同じスニーカーで色違いなだけで、グリップ感が違うということは個体差があるということなので、もしかしたら、あなたのスニーカーが特にグリップ感が弱くスリップするような感触があるとしたら、そのシューズは棒ノ折山のこのコースには向かないかもしれません。
その辺はご自身でしっかり判断をしていきましょう!
そして、スニーカーの性能だけでなく、歩き方も重要ですよね。これから、そのポイントを3つにまとめ説明していきます。自分が棒ノ折山のゴンジリ峠を歩いているのをイメージしながら読んでいただくといいと思います。ゴンジリ峠から山頂までの登り坂。何となく頭でイメージができたら、実際に普段の生活の中で、階段を登るときや上り坂・下り坂の時に少し思い出してやってみてください。
では、本題のポイント3つです♪
| ポイント① | 急登や階段の登りは、ジグザグ小股で! |
| ポイント② | 山下りは、後ろ足に重心を置く! |
| ポイント③ | トレッキングポールを使った歩き方を覚えよう! |
ポイント① 急登や階段の登りは、ジグザグに進む!
急な登りや階段が続く場合は、山に向かって直進するよりも、ジグザグに登るようにすると、距離は少し長くなりますが、1歩1歩に使うエネルギーが小さくなるので、余計な労力を使わずに済む効率の良い動作になり、疲れにくくなります。

そして、すごく急な場所では少し足をガニ股気味にして小股で進むと、下半身の筋肉、特に大きい筋肉である太もも・お尻の筋肉をしっかり使いやすくなるので、どこか1ヶ所に負担が集中せずに分散されてケガの予防ができます。

(関連記事)→「城峯山にワークマンのスニーカーで登る時の4つのコツ【理学療法士が教えます】」
また、登る際に、ザックを背負った上体が前のめりになりすぎてしまう方がいます。なぜこのようになってしまうかというと、『下半身や体幹の筋力が足りないかも!』というサインです。
登りが急になってくると、やや前傾になると思いますが、「前のめり」になるのとは少し違います。視線は下へ向き、上体が丸くなる感じが「前のめり」で体幹の力が抜けているような姿勢です。ゴンジリ峠から棒ノ折山山頂も徐々に登ります。少し姿勢を意識して体幹に力を入れる感じで行ければいいですね♪
山歩き当日に登りながら気をつけることではないかもしれませんが、「山歩きを続けていこうかな」と考えている方には、特にやってみて欲しいことは筋力トレーニングです。
「筋力トレーニング」と言っても、軽いものでいいのですが、ちょっと抵抗がある方や自信がない方は、まずは筋肉を鍛える前に、筋肉を伸ばすこと「ストレッチ」から始めましょう!


フォームローラーを使用するのもおすすめです♪
ストレッチをすることで、関節が少しづつ大きく動くようになり、山歩きの際、ある程度どんな場所にも対応できるだけでなく、柔かい筋肉は硬い筋肉よりよく伸び、関節が大きく動くのでケガをしにくくなります。ただし、柔らかいだけでもケガをしやすいので筋力も一緒につけていくイメージをするといいと思います。
実際にストレッチは、ストレッチ系YouTuber「オガトレ」さんの動画がわかりやすいと思うので、参考にしてみてくださいね!オガトレさんは理学療法士で、私は勝手に親近感があるだけなんですが(^^)笑
(参考)Youtube【「オガトレ」さんの『股関節』超硬い人向けシリーズ】
筋力トレーニングのおすすめは、まず、しっかりと『スクワット』ができるようになりましょう!!スクワットは全身の筋肉を鍛えるには基本のトレーニングで習得すると他の筋トレもやりやすくなるはずです!あなたには、ぜひ「カッコいい」スクワットができるようになって欲しいなあと思います(๑>◡<๑)
ポイント② 山下りや下り階段は、後ろ足に重心を置きながら下る!
下りだと重力に従って歩行速度が自然と早くなってしまいますよね。それに任せてガンガン下っていくと早く下山できてスケジュール的にはいいのかも知れませんが、膝や足の関節やふくらはぎや太ももの筋肉に、そのツケが回ってきてしますのです。
「下りの方が筋肉痛になる」って、あなたは聞いたことありますか?
下る時に発生するエネルギーを着地の時に支えているのは、骨や関節、筋肉です。ジャンプした後の着地は、体重の約4倍もの重さがかかっていると言われます。
山下りは片脚でそれを支える繰り返しです。片脚の筋力で勢いを殺しながら自分でコントロールし、足を着く場所を瞬間的に探し進んでいくので、急であればあるほど慎重さが必要になります。
その為、1歩または1段下るとき、「踏み出した足と反対の足(後ろの足)の方に重心置きながら、少しづつ重心移動して着地する」ようにすると着地の際の関節への衝撃は避けることができます。

ポイント③ トレッキングポールを使った歩き方を覚えよう!
トレッキングポールは、主に2種類あって、「ダブルで使うI型」と「シングルで使うT型」があります。
 ダブルで使うI型は、アップダウンが多いところや滑りやすいところ、ガレ場のあるところで使うのに向いています。推進力やバランス感覚をサポートしてくれる働きをします。
ダブルで使うI型は、アップダウンが多いところや滑りやすいところ、ガレ場のあるところで使うのに向いています。推進力やバランス感覚をサポートしてくれる働きをします。
シングルで使うT型は、アップダウンの少ないところやハイキングなどに向いています。

使うところやご自分の体力や痛めやすい部位がどこなのかによって、選ぶといいと思うのですが、迷ったら、I型をオススメします!!
I型は、アップダウンのある所に向いていると書きましたが、もちろん平地でも使えますし、ノルディックウォーキング(※杖先のゴムを変えれば)でも使えると思います。※参考→日本ノルディックウォーキング協会
また、少し体力に自信がない方は特にトレッキングポールを使うと少し楽に感じて快適に歩けるのではないかと思います。私も、初めて使った時は『こんなに違うのか!!』と驚いたくらいです。
今回は、I型のトレッキングポールを使い方について説明していきますよ♪
登りの時は、短め!下りの時は、長め!
トレッキングポールの長さは、身長によって変える必要があります。多くのポールが伸縮するタイプなので自分に合った長さを知っておきましょう。基本的に、平地使用時は、立位で肘を直角に曲げた時、グリップが握りやすい長さにします!
| 平地の時 | 立って、肘を直角にした時の床から手首までの高さ | |
| 登りの時 | 平地の時の長さ − 15cm | 注意ポイントなど |
| 下りの時 | 登りの時の長さ + 15cm |
ウォーキングなど、合わせた長さで試してみて微調整して使うといいと思います。
あとは、当日使い出してから、その時の環境に合わせて微調整が簡単にできるので安心してください♪♪
グリップの持ち方は、登りと下りで使い分ける!
| 登り |  |
ストラップのループに下から手に通して、そのストラップの根元部分と共にグリップを握ります。こうすると、握力だけでなく手首にストラップがかかり荷重を分散してくれて楽です。 |
| 下り |  |
グリップのトップの部分に手のひらを置き、軽く包むように握ります。登り同様に持ってもいいのですが、体重をかけ過ぎると手首に負担がかかり過ぎる傷める可能性があるので注意。 |
トレッキングポールを使った歩き方【登り・下り】
登り坂・下り坂によって、歩き方を変えますが、それはトレッキングポールを使っても同じです。
下の表にまとめてみました。基本的には、登り・下りの歩き方がしっかりできていれば、それにトレッキングポールで補助するイメージですが、注意ポイントはトレッキングポールに体重をかけ過ぎないことです!さすがに、腕に負担がかかりますし、ポールの強度にもよりますが、破損したりする原因にもなるので気をつけましょうね♪
| 登り |  |
登りでは、次に出す足の位置の少し前方に、反対側のトレッキングポールを着き、左右交互にそれを繰り返します。例えば、右足と左手ポール、左足と右手ポールに…と重心を移しながら後ろになる足を引き上げるという感じ。トレッキングポールは垂直に着きます。 |
| 下り |  |
下りでは、次に出す足の真横か、一段下にトレッキングポールを着いてから、足を着地させます。歩幅は平地の半分くらいにして、体重がポールにかかり過ぎないようにしましょう。 |
トレッキングポールは、上手く効率よく使うと、足腰への負担も軽減できるのでケガを予防につながるし、体力消費も節約でき疲労しにくく少しつづ色んな山を歩くこともできるようになっていくと思うので、活用していきましょう♪
1都6県ぐるりと1周する「関東ふれあいの道」
まず、「関東ふれあいの道」とは?
関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)は、東京都の高尾山を起終点に、関東1都6県(東京、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈川)を延長1,799キロメートル、160のコースで一周する長距離自然歩道です。
そのうち、埼玉県分は、飯能市の棒の嶺から、奥武蔵の山々、長瀞を通り、神川町の下久保ダムへ抜ける13コース、延長155.5kmとなっています。
関東をぐるりと1周する長ーーーーいコースになっているとは、驚きましたΣ(‘◉⌓◉’)
各都県に幾つものコースがあり、160ものコースが繋がりあって
約1800km!!!!!
 (出典:環境省「首都圏自然歩道(関東ふれあいの道)について」より)
(出典:環境省「首都圏自然歩道(関東ふれあいの道)について」より)
なんか少しづつ歩いて、制覇したくなる♪( ´▽`)ワタシダケ?
埼玉県コースの全コースを見たい方は、↓こちらを参考に♪
その中でも、今回の「棒ノ折山(棒ノ嶺)」にかかる埼玉県コース1「水源のみち」について、もう少し深掘りしたいと思います。
【関東ふれあいの道】埼玉県コース1:水源のみち
埼玉県のコースは、155.5km、13コースが設定されていて、その一つ目が「水源のみち」で、東京都との境である「棒ノ嶺(棒ノ折山)」から始まり、「三波石峡」を通って群馬県と結ぶ。
(出典:環境省 「首都圏自然歩道(関東ふれあいの道) 埼玉県 コース紹介 01.水源のみち」より)
| 距離 | 8.9km |
| 所要時間 | 3時間 |
| 難易度 | ★★★⭐︎⭐︎ |
| 区間 | 上日向バス停 〜 百軒茶屋 〜 棒ノ嶺(棒ノ折山) 〜 ゴンジリ峠 〜 岩茸石 〜 有馬ダム 〜 河又・名栗湖入口バス停 |
| 撮影スポット | 白孔雀の滝地名坂 |
コース踏破の認定証が発行されるらしいのですが、全コースの写真が揃ったら申請し、審査を通れば各県の記念バッジがいただけるようです!
その時、各コースで撮影スポットが決められているので、その場所で撮った写真が必要ということだそうです!
「水源のみち」の撮影スポットはこんな感じのところですよ↓

この滝の脇を登っていくそうですが、ここが沢登りで有名なところですね♪ゴルジュ帯のステキな雰囲気も味わいたいですね(´ ▽ `)
まとめ
| ポイント① | 急登や階段の登りは、ジグザグ小股で! |  |
| ポイント② | 山下りは、後ろ足に重心を置く! |  |
| ポイント③ | トレッキングポールを使った歩き方を覚えよう! |  |
体の動かし方というのは、人によって習得時に個人差があると思います。私たちの歩き方がみんな違うように、山の歩き方も少しづつ違って当たり前かもしれませんが、コツを体が覚えたらその自分の歩き方も、より効率のいいこれからも楽しく山歩きが続けていける体の動かし方の習得ができたと言えるんだと思うのです。
あなたにとっての山歩きライフが楽しくなるように情報をこれからもまとめていきますね♪

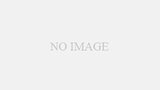
コメント